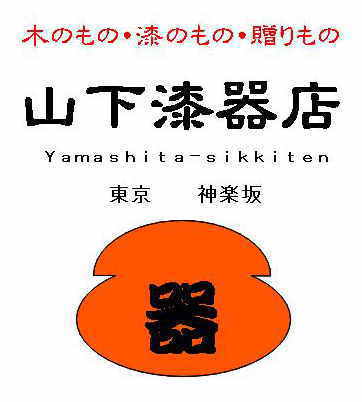|
飛騨春慶塗
山に囲まれた飛騨の国は、昔より良木に恵まれていました。
奈良、平安の時代には、都造りの多くの用材がこの地から運ばれたとの記録にも残されています。
森から木を切り出す杣人、板を挽く木挽、…その中には木工に巧みな者もあらわれ、飛騨匠の輪郭をしだいに浮かび上がらせてきました。
慶長年間、匠たちのすぐれた技を母体に春慶塗が生まれました。
その当時、高山藩主二代目、金森可重は飛騨の各地に神社仏閣を築造していました。ある日、大工棟梁高橋喜左衛門が斧を振るって椹(さわら)の木を打ち割ったところ、その割れ目に見事な木目があらわれたので、盆をつくり、可重の子、重近(茶道宋和流の開祖)へと献上しました。
重近はその雅趣を喜び、藩のご用塗師、成田三右衛門義賢に命じ塗らせました。
成田はこの盆を木目を活かした透明な塗りに仕上げ、これが春慶塗の始まりといわれています。
匠の技の冴えを見せる木地、人を魅了するやさしい朱色の彩り、その美しさは、簡素でありながら独特の風雅をかもしだします。
抹ィの味わいをわたし立ちに語りかけてくれる、飛騨春慶塗。それは、まぎれもなく木の国・飛騨が生んだ伝統工芸です。
飛騨春慶は塗り上げ後、数ヶ月位経過すると、次第に透明度を増してきます。しかし、その間は漆の中の油分がしみだし、表面にくもりを生じます。その場合には、柔らかい布でふき取ってください。油分をふき取らないで長期間放置された場合は、アルコール又は揮発油でふき取ってください。
これは、漆が樹液であるため、記地と一体となる性質を持っており、完全に乾くまで長い時間が必要とするためで、天然の塗料の証でもあります。
|